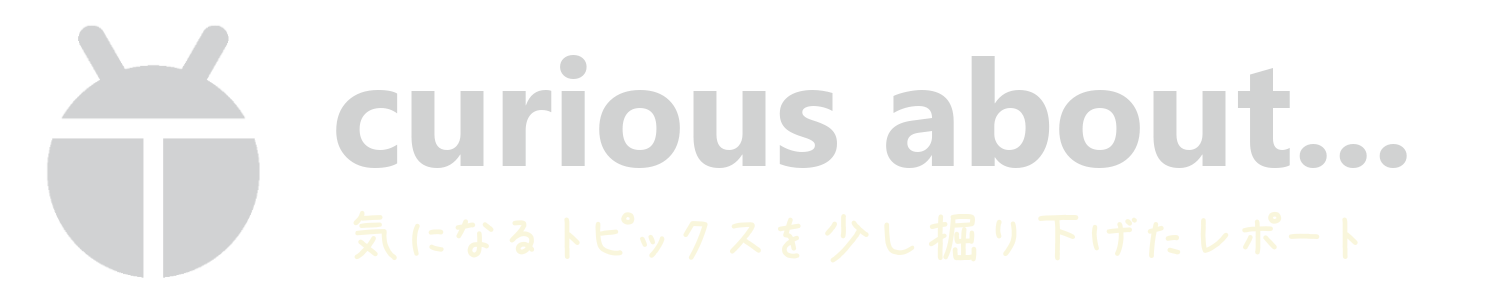クレーム対応
店舗で発生したクレームの処理をしていた経験から言えば、「これを抑えておけば大丈夫」といった虎の巻は存在せず、「誰かの真似」をして成功するものでもないが、クレーム対応は怒っている客をなだめることではなく、どれほどのクレームであっても、所詮は仕事上のトラブルに過ぎず、仕事上のトラブルであれば仕事上で解決できる。
怒っている相手を前に「冷静に対応する」というのは難しく、及び腰になるのは仕方がないが、威嚇してくる相手が恐れているのは「動じない」ことなので、普通に受け答えをしているだけでトーンダウンするケースも多々ある。
大きなクレームになると一日二日で解決するものでもなく、閉塞感や孤独感があって精神的にかなり厳しいが、岡目八目とはよく言ったもので、傍から見れば大した問題でもないものが、クレームの渦中にいる当事者になると、往々にして視野が狭くなり物事の本質を見失うため、「何を可しとし、何を否とするのか」を自分の中でしっかりと持ち、法律を正しく理解しておくと対応にも余裕が生まれてくる。
場数を踏んでいるクレーマーであれば「責任者を出せ」「社長を呼んでこい」「消費者センターに訴える」「知人に弁護士がいる」「裁判を起こす」などの常套句を使って揺さぶりをかけ、担当者には「おおごとにしたくない」「早く終わらせたい」という気持ちが働くため、毅然とした応対をするにも会社や上司の協力は不可欠で、事前にしっかりと対応方法を確認しておくことが重要。
クレーマーが常套手段として「AでないということはBということだな」といった二択を迫るのは、人は選択できない二択を迫られると思考が停止してしまうからで、そもそも真っ正直に相手の二択に答える必要はないのだが、クレーム対応の当事者になるとその判断すらできなくなるケースが多い。
場合によっては弁護士や警察に相談することにもなるので、どのようなクレームでも、電話の場合は通話録音、直接対応した場合は 話した内容をできるだけ詳細に記録しておく。
交渉の着地点
法律用語での「和解」は「互いに譲歩」することを意味しており、クレーム交渉でも「要求の一部承諾」が解決策としては現実的な着地点になるため、クレームが発生した時点で譲歩する着地点を決め、不当な要求であれば完全拒否を目標に交渉し、状況に応じて着地点まで譲歩して納得してもらう。
正当か不当かに関わらず要求を拒否する場合は、相手を激怒させて事態が悪化するリスクも多分にあり、相手が消費者センターへの連絡はもとより、 SNS での中傷拡散などを行う可能性なども含めて検討が必要なため、会社側の協力が不可欠になる。
会社や上司がクレームを面倒な厄介事としか認識していないと、担当者は客と会社の双方で交渉が必要になり、折り合いがつかない場合は 担当者だけが精神的に疲弊するという最悪の状況に陥ってしまう。
実際、現場では 担当者が上司から「なんとかしろ」と言われ、 客との板挟みになって為す術もなく悩んでいることが多く、クレームを収めるために身銭を切ったという話しも少なくない。
消費者センター
消費者センターは一方的に消費者の言い分を聞くわけではなく、告発されている業者へも電話で聞き取りを行って状況を判断しており、仮に告発されても客への対応が正当であれば突き通すこともできる。
2009年 9月に消費者庁が発足して以降 「消費者センター」は 消費者庁と連携するようになり、重大事故などの情報を消費者庁に提供するようになったが、業者に対して勧告や立ち入り調査などの直接権限は持っておらず、一般的な問題については「仲裁役」として助言がある程度で、相談の内容によっては法律などを説明して受け付けない場合もある。
「消費者センターに訴える」はクレーマーの常套句の1つだが、対応に問題がなければ 消費者センターに訴えても諭されるか、連絡が入ったとしても状況を説明するだけで解決し、場合によっては消費者センターの担当者に同情までされるので、厄介なクレームは消費者センターに訴えてくれたほうが精神的な負担が随分と軽減される。
売買契約
専門店や食品スーパー、百貨店などで日常的にしている買い物は、民法 第555条に定める「売買契約」が成立している。
民法 債権 (売買)
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
売買契約は申込みと承諾を必要とする「諾成(だくせい)契約」で、売主と買主の双方に債務が発生する「双務契約」になり、売主には目的物引渡義務 、買主には代金支払義務が発生し、契約の成立条件については 書面作成は必須ではなく「口頭の合意」でも成立する。
レジなどで日常的行われている買い物のやりとりは、買主が購入の意志表示を行い、売主がそれを承諾し、口頭の合意の元に売買契約が成立しており、販売員が接客して商品を勧めても、客が納得しなければ諾成契約が不成立になるので売買は行われない。
店舗ではまず見られないやりとりだが、諾成契約の性質上、買主の申込みを売主が拒否することもできる。
契約自由の原則 という近代法の原則では「契約関係は当事者の自由な意思によって決定し 国家は干渉しない」とされ、日本では「締約の自由」「相手方選択の自由」「内容の自由」「方式の自由」から構成されている。
小売店は商品を販売しているが「商品を客に売る義務」はなく、来店した客の購入をすべて断っても法律的には問題ない。
販売には「売らない選択肢」があり、販売しなければ商品クレームは発生しないため、極論になるが クレームになるリスクがある客には販売しない のがクレームを未然に防ぐ上策になる。
債務不履行責任
売買契約が成立すると売主と買主の双方に「完全な履行をする義務」が生じ、売主は目的物(商品)の引き渡し、買主は代金を支払って契約が履行されるが、サイズ違いや色違いなど間違った商品を渡してしまった場合は、売主側の「債務不履行」になるため、正しい商品と交換して売買契約を履行するか、契約を解除して売買の目的物(商品)と引き換えに返金することになる。
債務不履行が発生した場合、売主は契約違反を犯したことになるが、買主からのクレームに対しては日常的に裁判をせずに和解(示談)が行われている。
善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
販売店での商品取り扱いについては、既製品などの「不特定物・種類物」の場合は 自己の財産におけるのと同一の注意義務 が必要で、客が購入を決めた「特定物」になると 善良な管理者の注意義務 が生じる。
民法 債権 (特定物の引渡しの場合の注意義務)
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは「債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意」のことで、立場に相応しい最善の仕事が要求されている。
クレームの際には「それくらいは当たり前」とか「それくらいは常識」と言われることが多い。
何をもって常識とするのかは判断が難しいところだが、「不具合のある商品の販売」は債務不履行になるため、販売時もしくは入荷時の検品は「善管注意義務」に該当すると考えられる。
商品の検品については 商法 第526条 (買主による目的物の検査及び通知)で、買主は目的物を受領したときは 速やかに 目的物の検査をすることが義務付けられているが、これは「商人間( B to B )の売買」のことであって一般消費者を対象とした小売( B to C )には適用されない。
契約不適合責任
2020年 4月1日より施行される改正民法では「瑕疵担保責任」が廃止され、特定物・不特定に関わらず「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は 売主が「契約不適合責任」を負うことになる。
契約不適合責任は「債務不履行」の損害賠償請求条件に準じ、「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は賠償請求はできない(改正民法415条)とされている。
購入したシャツの一部分が縫えていないことを発見した場合は「契約の内容に適合しないもの」と見なされ、売主は債務不履行になるため、商品を交換して売買契約を履行するか、契約を解除して売買の目的物(商品)と引き換えに 返金が必要だが、シャツの縫製不良は販売店の責任ではないため、シャツの縫製不良によって損害を被ったとしても売主への賠償請求は難しい。
賠償請求 – 交通費
債務不履行によって被った被害については賠償請求できるが、賠償請求は 現実に損害が生じなければ請求できず、損害の被害額を証明する必要もある ので、通常は売買契約の「完全な履行をする義務」を再履行する形で示談が成立していることが多い。
実店舗の場合、商品交換や返品の際に来店するように言われることもあるが、売主のミス( 売主の過失 )で返品や商品交換が発生し、買主が商品交換のために交通費を使って店舗まで来た場合、法律的に買主は店舗までの往復交通費を売主に請求できる。
ただし、賠償請求する権利はあるものの、請求額や支払いについては 交渉になり、売主の提示条件に納得できない場合は民事訴訟になる。
現実的には 売主の過失で交通費が発生したとしても 交通費を請求する買主は少なく、交通費の請求拒否で少額裁判を起こすような人も 皆無に近いため、売主が法律を理解しておらず、交通費の請求を不当だと思い込んでいるケースも多い。
クーリングオフの誤解
「 一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除 」できるクーリング・オフ制度は、訪問販売やマルチ商法などを対象にしており、通信販売も実店舗での物販も含まれていない。
現行法にクーリングオフという表記はない。
特定商取引に関する法律 (通信販売における契約の解除等)
第15条の3
通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
「 特定商取引に関する法律 第15条の3 」で定められている通信販売の 返品特約 には、通販の場合は返品特約として記載がない限り、 商品を受け取ってから8日間は契約の解除(返品返金)できると規定されており、これを都合よく端折って「商品は購入から1週間以内であれば返品返金できる」と拡大解釈をしている消費者が非常に多い。
売主には 善管注意義務 や 契約不適合責任 が義務付けられ、消費者は手厚く保護されているが、実店舗での販売は客が自らの意思で来店して物品を購入するため、販売側が能動的に動く訪問販売やマルチ商法、キャッチセールスなどに適用されるクーリング・オフは対象外で、「 通信販売における契約の解除等 」についても 通販に限った項目のため、実店舗での販売は含まれない。
債務履行時の返金返品
購入した商品が未使用でレシートがあれば、交換や返品返金に応じる小売店は多いが、本来 契約した当事者はその契約に拘束され、その内容を守る義務を負い、一方的な契約の解除や変更はできないため、売主は売買において「債務の完全な履行」をしていれば、買主との売買契約は代金と商品を引換えた時に締結しており、商品交換や返品返金をする義務や責任はない。
実店舗の場合は客が選んだ商品を引き渡し、その代金を受け取って売買契約を締結しているため、商品に問題がない(債務を履行)している場合、買主が一方的に契約解除(返品返金)や変更(商品交換)はできないが、店側が顧客サービスとして行っていることが当たり前になり、自覚がないまま不当な要求をしている人が増えている。
また、店側も事なかれ主義的な対応をしているところが多く、クレーム対応にかかる労力と精神的負担や売り場で大声を出されるリスクなどを考慮すると、多少のロスが生じても丸く収めたいという心理が働き、相手都合の返品交換を会社が認めている場合は、安易に返品交換の処理をするようになり、クレーム処理は客の要求を飲むのが当たり前になり、その結果として消費者に「要求は通るもの」という誤った認識を与えことになる。
近年はコンプライアンスが厳しくなったが、バブル崩壊まで大きな販売力をもっていた百貨店は、メーカーに「優位的地位」にあり、商品の入れ替えや返品などの無茶振りは日常茶飯で、客のクレームによる損失もメーカーに丸投げしていた時期があり、メーカーも売上が伸びているため、多少のロスは黙認するという関係にあった。
「客都合の返品交換」は百貨店の代表サービスになり、同時期に百貨店を模倣して勢力を拡大していた総合スーパー(GMS)も百貨店に追随する形で「客都合の返品交換」を許容し、消費者が認知するスタンダードなサービスになった。